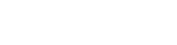近世における落雷による事故4
◆享和元年12月4日(1802年1月7日)
大阪天王寺の塔に落雷があり、火災により塔、金堂、七堂伽藍などが焼失する(摂陽奇観、享和雑記、続日本王代一覧、池魚録)。
◆享和3年6月5日(1803年7月23日)
琉球沖縄島で落雷があり、家屋に被害がでる(球陽)。
◆文化2年12月27日(1806年12月27日)
琉球沖縄島で落雷があり、家屋に被害がでる(球陽)。
◆文化3年6月22日(1806年8月6日)
因幡城天守閣、太鼓門に落雷があり、門を破損する(因府年表、日本史分類年表)。
◆文化4年9月2日(1807年10月3日)
沖縄島で落雷により死者がでる(球陽)。
◆文化4年9月2日(1807年10月3日)
加賀国金沢で落雷により甲斐守の屋敷に落雷がある(政隣記)。
◆文化7年4月3日(1810年5月5日)
長門国(現在の山口県北西部に相当)門司で落雷のため、船が破損する(半日閑話)。
◆文化7年7月7日(1810年8月6日)
因幡国の民家に落雷がある(因府年表)。
◆文化8年4月19日(1811年6月9日)
琉球沖縄島で落雷があり、家屋に被害がでる(球陽)。
◆文化8年7月30日(1811年9月17日)
因幡国権現堂付近の民家に落雷がある(因府年表)。
◆文化10年6月13日(1813年7月10日)
京の大内裏にある建春門に落雷がある(野史)。
◆文化11年7月16日(1813年8月11日)
因幡国で風呂屋に落雷がある(因府年表)。
◆文化12年4月9日(1815年5月17日)
伯耆国八橋沖で落雷により船が焼失する(因府年表)。
◆文化12年8月7日(1815年9月9日)
琉球沖縄島で落雷により家屋に被害がでる(球陽)。
◆文化13年3月20日(1816年4月17日)
琉球沖縄島で落雷により死者がでる(球陽)。
◆文化13年5月7日(1816年6月2日)
因幡国で落雷により1名が亡くなる(因府年表)。
◆文化13年7月4日(1816年7月28日)
紀伊国で落雷のため子供が亡くなる(熊野史)。
◆文化13年6月10日(1816年7月4日)
琉球沖縄島で落雷により2名が亡くなる(球陽)。
◆文化14年7月22日(1817年9月3日)
因幡国京福寺に落雷がある(因府年表)。
◆文政元年9月4日(1818年10月3日)
江戸今戸に落雷があり、死者がでる(東京市史稿)。
◆文政元年4月7日(1818年5月11日)
江戸虎ノ門にある京極上屋敷に落雷がある(東京市史稿)。
◆文政2年6月25日(1819年8月15日)
沖縄島に落雷があり、死者がでる(球陽)。
◆文政2年6月11日(1819年8月1日)
沖縄島に落雷があり、女性が亡くなる(球陽)。
◆文政3年5月3日(1820年6月13日)
沖縄島に落雷があり、死者がでる(球陽)。
◆文政3年6月6日(1820年7月15日)
江戸で雷雨があり、吉原、小日向、本石町、芝金杉などに落雷がある(武江年表、東京市史稿)。
◆文政4年9月7日(1821年10月2日)
江戸の下谷、三味線堀、飯田町、堀留、愛宕下藪小路などに落雷がある(東京市史稿)。
◆文政4年7月19日(1821年8月16日)
江戸で雷雨があり、日本橋に落雷がある(武江年表、東京市史稿)。
◆文政5年3月3日(1822年4月24日)
江戸の麻布、浅草などに落雷がある(東京市史稿)。
◆文政5年6月9日(1822年7月26日)
大阪船場で落雷により、少女が亡くなる(摂陽奇観)。
◆文政5年6月29日(1822年8月15日)
武蔵国渋谷、青山、瀬田谷などに落雷がある(東京市史稿)。
◆文政6年7月12日(1823年8月17日)
江戸の小日向、牛込、市谷、番町などに落雷がある(東京市史稿)。
◆文政7年3月12日(1824年4月10日)
琉球沖縄島で落雷があり、家屋に被害がでる(球陽)。
◆文政8年4月23日(1825年6月9日)
江戸麻布の遠山美濃守の屋敷に落雷がある(続日本王代一覧、東京市史稿)。
◆文政9年6月29日(1826年8月2日)
武蔵国銀座町、青山、駒場野、池上村に落雷がある(東京市史稿)。
◆文政10年11月20日(1828年1月6日)
和泉国岸和田城天守閣に落雷があり、焼失する(摂陽奇観、日本史分類年表)。
◆文政11年7月1日(1828年8月11日)
京都大仏殿に落雷があり、焼失する(宝暦現来集、日本史分類年表)。
◆文政12年6月10日(1829年7月10日)
武蔵国江戸城、日本橋、八丁堀、三十間堀、牛込、小日向、根津、谷中、下谷、本所、市谷、青山、渋谷、羽沢、下目黒、増上寺などに落雷がある(東京市史稿)。
◆天保元年5月28日(1830年7月18日)
武蔵国林肥後守屋敷、本多上杉屋敷、増上寺下屋敷、紅葉山、一本松、芝永井町、市谷、青山などに落雷がある(東京市史稿)。
◆天保2年4月8日(1831年5月19日)
江戸芝に落雷があり、2名が亡くなる(東京市史稿)。
◆天保2年6月20日(1831年7月28日)
江戸各地に落雷があり、阿部伊予守の屋敷で1名がなくなった他、各地で死者が多数でる(東京市史稿)。
◆天保3年1月25日(1832年2月26日)
琉球伊平屋島に落雷があり、死者がでる(球陽)。
◆天保3年3月5日(1832年4月5日)
江戸両国で落雷により、女性が亡くなる(東京市史稿)。
◆天保4年1月29日(1833年3月20日)
琉球沖縄島で落雷があり、家屋に被害がでる(球陽)。
◆天保5年2月218日(1834年3月27日)
江戸の東叡山に落雷がある(東京市史稿)。
◆天保6年3月12日(1835年4月9日)
因幡国で落雷があり、3軒焼失する(因府年表)。
◆天保6年6月13日(1835年7月8日)
下総国(現在の千葉県北部と茨城県南西部に相当)で民家に落雷がある(香取郡誌)。
◆天保7年6月9日(1836年7月22日)
因幡国で落雷により1名が亡くなる(因府年表)。
◆天保10年4月(1839年5月13日から6月10日)
沖縄島に落雷があり、死者がでる(球陽)。
◆天保10年4月5日(1839年5月17日)
筑前国(現在の福岡県北西部)に落雷があり、船頭などが亡くなる(福岡県災異誌)。
◆天保11年6月5日(1840年7月3日)
農家に落雷があり、3名が亡くなる(因府年表)。
◆天保11年7月5日(1840年8月2日)
沖縄島に落雷があり、死者がでる(球陽)。
◆天保11年8月29日(1840年9月24日)
沖縄島に落雷があり、2名が亡くなる(球陽)。
◆天保12年4月16日(1841年6月5日)
因幡国で落雷があり、死者がでる(因府年表)。
◆天保13年3月7日(1842年4月17日)
琉球宮古島に落雷があり、家屋に被害がでる(球陽)。
◆天保14年3月28日(1843年4月27日)
沖縄島に落雷があり、死者がでる(球陽)。
◆弘化元年2月11日(1844年3月29日)
沖縄島に落雷があり、死者がでる(球陽)。
◆弘化2年(1845年)
山陰地方で落雷があり、5人死亡する(日本史分類年表)。
◆弘化3年(1846年)
越後国に落雷があり、40人死亡する(日本史分類年表)。
◆弘化3年閏5月28日(1846年7月21日)
江戸本所回向院の境内に落雷がある(天弘録)。
◆弘化3年6月3日(1846年7月25日)
江戸湯島の村田阿波守の屋敷に落雷がある(続泰平年表拔萃)。
◆弘化3年6月27日(1846年8月18日)
美濃国大垣の17、8ヶ所で落雷がある(大垣市史)。
◆弘化3年7月26日(1846年9月16日)
紀伊国和歌山城で落雷により天守閣・槽・多門が焼失する(南紀徳川史)。
◆嘉永2年9月20日(1849年11月4日)
下総国で落雷のため死者がでる(巷街贅説)。
◆嘉永2年4月3日(1849年4月25日)
沖縄島で落雷があり、家屋に被害がでる(球陽)。
◆嘉永3年8月8日(1850年9月13日)
江戸の薬研堀など100ヶ所以上に落雷があり、被害がでる(池魚録、武江年表、今日抄、東京市史稿)。
◆嘉永3年7月21日(1850年8月28日)
沖縄島で落雷のため死者がでる(球陽)。
◆嘉永5年6月17日(1852年8月2日)
琉球沖縄島で落雷により家屋に被害がでる(球陽)。
◆嘉永5年6月18日(1852年8月3日)
上野国(現在の群馬県に相当)向町橋林寺が、落雷のため焼失する(日本災異史)。
◆安政元年5月12日(1854年6月27日)
江戸深川扇橋の細川候の中屋敷に落雷があり、焼失する(武江年表)。
◆安政3年2月21日(1856年3月27日)
沖縄島に落雷があり、死者がでる(球陽)。
◆安政3年4月27日(1856年5月30日)
沖縄島に落雷があり、死者がでる(球陽)。
◆安政4年1月2日(1857年1月27日)
伊豆国(現在の静岡県東部)下田で落雷のため、船が破損する(続徳川実紀、嘉永明治年間録)。
◆万延元年8月3日(1860年9月17日)
琉球宮古島で船に落雷があり、1名が亡くなる(球陽)。
◆文久3年4月25日(1863年6月11日)
琉球沖縄島で落雷があり、親子2名が亡くなる(球陽)。
◆元治元年8月10日(1864年9月10日)
琉球沖縄島で硫黄などが保管してある倉庫に落雷がある(球陽)。
◆慶應元年6月23日(1865年8月14日)
江戸の神田川の周辺、柳原、本所、浅草などに落雷がある(武江年表)。
◆慶應3年7月28日(1867年8月27日)
筑前国で落雷があり、4人死亡する(福岡県災異誌、日本史分類年表)。
参考文献
- 「日本の災害史(第1巻〜第4巻)」(著者 三浦幸一郎 発行所 三浦幸一郎)
- 「日本史小百科 災害」(著者 荒川秀俊、宇佐美龍夫 発行所 近藤出版社)
- 「日本の天災・地変 上・下」(編集 東京府社会課 発行所 原書房)
- 「日本史分類年表」(著者 桑田忠親 発行所 東京書籍)
- 「雷の話」(著者 神田選吉 発行所 電友社)
- 「名前から引く人名辞典」(編集 日外アソシエーツ 発行所 日外アソシエーツ)
- 「日本史総覧」(監修 児玉幸多/他 発行所 新人物往来社)
- 「国史大系」(編集 黒板勝美、国史大系編修会 発行所 古川弘文館)
- 「日本叢書索引」(編修 広瀬敏 発行所 名著刊行会)
- 「古典籍総合目録」(編集 国文学研究資料館 発行所 岩波書店)
前のページへ
落雷による事故が記載されている元の文献へ
雷の事故のページへ