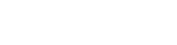近世における落雷による事故3
◆宝暦11年2月11日(1761年3月17日)
伊江島に落雷があり、家屋に被害がでる(球陽)。
◆宝暦11年4月12日(1761年5月16日)
宮古島に落雷があり、若者が雷にうたれて亡くなる(球陽)。
◆明和元年6月(1764年6月2日から7月28日)
北海道支利宇知社に落雷があり、1名が亡くなる(新撰 北海道史)。
◆明和元年8月18日(1764年9月13日)
能登国(現在の石川県北部)に落雷があり、七十軒以上が焼失する(泰雲公御年譜)。
◆明和2年12月23日(1766年2月2日)
琉球八重山で落雷により家屋が焼失する(球陽)。
◆明和3年5月23日(1766年6月29日)
沖縄島で落雷があり、死者がでる(球陽)。
◆明和4年7月28日(1767年8月22日)
仁親親王の屋敷に落雷がある(続史愚抄)。
◆明和5年6月16日(1768年7月29日)
江戸城竹橋門に落雷があり、焼失する(柳営年表秘録、日本史分類年表、武江年表、徳川実紀)。
◆明和6年9月5日(1769年10月4日)
琉球八重山島で落雷のため、死者がでる(球陽)。
◆明和6年6月23日(1769年7月26日)
二条城、相國寺、蓮花光院、前菅大納言東坊城綱忠、入道前中納言坊条俊逸、左少将隆房の屋敷に落雷がある(続史愚抄)。
◆明和7年2月6日(1770年3月2日)
琉球沖縄島で牛に落雷があり、死亡する(球陽)。
◆安永3年2月2日(1774年3月13日)
二条大納言治孝の屋敷、建仁寺が落雷のため被害がでる(続史愚抄)。
◆安永3年6月6日(1774年7月14日)
護国寺、市橋大膳、松平筑前守、竹中伊予守、松平讃岐守、松平安芸守、岡部内膳正、井上河内守、松平越前守の屋敷などに落雷がある(半日閑話、泰平年表、武江年表)。
◆安永4年8月11日(1775年9月5日)
京都大仏殿に落雷があり、火災が発生する(続日本王代一覧、続史愚抄、新東鑑)。
◆安永5年6月(1776年7月16日から8月13日)
大坂に落雷があり、多くの人が亡くなる(続日本王代一覧)。
◆安永6年4月4日(1777年5月10日)
沖縄島に落雷があり、家屋に被害がでる(球陽)。
◆安永6年4月19日(1777年5月25日)
八条隆輔の屋敷に落雷がある(続史愚抄)。
◆安永6年4月20日(1777年5月26日)
美濃国に落雷があり、家屋に被害がでる(大垣市史)。
◆安永7年6月22日(1778年7月16日)
大阪四天王寺の五重の塔に落雷がある(続史愚抄、徳川実紀、岡山市史、籠耳集、摂陽奇観)。
◆安永7年6月28日(1778年7月22日)
岡山大隣寺に落雷があり、本堂が焼失する(岡山市史)。
◆安永7年7月21日(1778年8月13日)
因幡国に落雷があり、死者がでる(因府年表)。
◆安永9年3月28日(1780年5月2日)
伯耆国(現在の鳥取県西部)の香宝寺が落雷のため焼失する(因府年表、因伯雑記)。
◆天明元年閏5月28日(1781年7月19日)
琉球島に落雷があり、死者がでる(球陽)。
◆天明2年2月30日(1782年4月12日)
琉球伊平屋島に落雷があり、死者がでる(球陽)。
◆天明3年11月11日(1783年11月5日)
大阪城の大手御門が落雷により焼失する(続日本王代一覧、徳川実紀、摂陽奇観、日本史分類年表)。
◆天明3年4月15日(1783年5月15日)
沖縄島に落雷があり、那覇港の船が破損したほか、家屋に被害がでる(球陽)。
◆天明4年1月1日(1784年2月21日)
伊予国(現在の愛媛県のあたり)松山城の天守閣が落雷により焼失する(日本史分類年表)。
◆天明5年7月7日(1785年8月11日)
因幡国鹿野街道の民家の土蔵に落雷がある(因府年表)。
◆天明5年7月9日(1785年8月13日)
大阪千日法善寺に落雷があり、7名が死亡する(摂陽奇観、続日本王代一覧)。
◆天明6年3月(1786年3月30日から4月27日)
北海道支利宇知社が落雷により焼失する(新撰 北海道史、日本史分類年表)。
◆天明7年8月28日(1787年10月9日)
美濃国に落雷があり、家屋が焼失する(大垣市史)。
◆寛政3年(1791年)
陸前国(現在の宮城県と岩手県の南部に相当する)に落雷があり、12人亡くなる(日本史分類年表)。
◆寛政3年3月25日(1791年4月27日)
沖縄島で落雷があり、1名が亡くなる(球陽)。
◆寛政7年6月15日(1791年7月30日)
松平遠江守、三浦長門守、松平豊後守、阿部豊後守、酒井修理大夫、神保右京、京極壱岐守の屋敷などに落雷がある(半日閑話、武江年表、続日本王代一覧、巷街贅説)。
◆寛政4年2月20日(1792年3月12日)
琉球粟国島に落雷があり、死者がでる(球陽)。
◆寛政7年6月28日(1795年8月12日)
稲垣摂津守、水戸大学、浅野壱岐守の屋敷、龍興寺、霊厳寺などに落雷がある(半日閑話)。
◆寛政8年2月10日(1796年3月18日)
沖縄島で落雷のため死者がでる(球陽)。
◆寛政8年2月12日(1796年3月20日)
沖縄島で落雷のため、死者がでる(球陽)。
◆寛政9年閏6月5日(1797年7月28日)
沖縄島で落雷のため、家畜の牛に被害がでる(球陽)。
◆寛政10年9月24日(1798年11月2日)
江戸本所の押上慈照寺院に落雷があり、火災で被害がでる(寛政紀聞)。
◆寛政10年7月1日(1798年8月12日)
京都大仏に落雷があり、本堂・仁王門・南門・回廊・仏像などが全焼する(続日本王代一覧、京大佛殿火災、新東鑑、甲子夜話、柳営年表秘録、永代年代記大成、続皇年代記、泰平年表)。
◆寛政11年10月18日(1799年11月15日)
琉球沖縄島で落雷のため豚が死亡する(球陽)。
◆寛政11年4月28日(1799年4月28日)
武蔵国浦和で落雷により死者がでる(寛政紀聞)。
◆寛政11年7月17日(1799年8月17日)
因幡国で畑にいた農民負債が落雷により死亡する(因府年表)。
◆寛政12年6月15日(1800年8月5日)
伯耆国に落雷があり、落雷に驚いて亡くなる人がでる(因府年表)。
参考文献
- 「日本の災害史(第1巻〜第4巻)」(著者 三浦幸一郎 発行所 三浦幸一郎)
- 「日本史小百科 災害」(著者 荒川秀俊、宇佐美龍夫 発行所 近藤出版社)
- 「日本の天災・地変 上・下」(編集 東京府社会課 発行所 原書房)
- 「日本史分類年表」(著者 桑田忠親 発行所 東京書籍)
- 「雷の話」(著者 神田選吉 発行所 電友社)
- 「名前から引く人名辞典」(編集 日外アソシエーツ 発行所 日外アソシエーツ)
- 「日本史総覧」(監修 児玉幸多/他 発行所 新人物往来社)
- 「国史大系」(編集 黒板勝美、国史大系編修会 発行所 古川弘文館)
- 「日本叢書索引」(編修 広瀬敏 発行所 名著刊行会)
- 「古典籍総合目録」(編集 国文学研究資料館 発行所 岩波書店)
前のページへ|
次のページへ
落雷による事故が記載されている元の文献へ
雷の事故のページへ