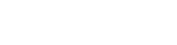中世における落雷による事故
◆建久7年8月17日(1196年9月11日)
京の八条堀川にある中納言兼左衛門督藤原隆房の屋敷に落雷があり、焼失する(百練抄)。
◆承元2年5月15日(1208年6月29日)
法勝寺の九重塔が落雷により焼失する(明月記、立川寺年代記、興福寺略年代記、帝王編年記、皇年代略記)。
◆承久3年6月8日(1221年6月29日)
鎌倉にある北条義時(2代目執権)の屋敷に落雷がある。(吾妻鏡)。
◆貞応元年6月18日(1222年7月28日)
京の冷泉宮に落雷がある(承久三年四年日次記)。
◆貞応元年6月18日(1222年7月28日)
鎌倉幕府の建物に落雷があり、1名が死亡する(吾妻鏡)。
◆嘉祿2年2月28日(1226年3月27日)
日吉八王寺に落雷があり、樹木に被害がでる(百練抄、明月記、吾妻鏡)。
◆嘉祿2年6月25日(1226年7月20日)
比叡山に落雷があり、1名が亡くなる。また、前関白の屋敷に落雷があり、被害がでる。(明月記、皇帝紀抄)。
◆安貞2年3月6日(1228年4月11日)
加茂社に落雷がある(百練抄)。
◆寛喜2年6月19日(1230年7月20日)
鎌倉幕府の御所に落雷がある(吾妻鏡)。
◆貞永元年3月2日(1232年3月25日)
東大寺、元興寺、春日社の塔に落雷があり、焼失する(百練抄、大日本史、皇帝紀抄)。
◆嘉禎2年6月20日(1236年7月24日)
平野社に落雷があり、被害がでる(百練抄)。
◆仁治2年1月8日(1241年2月20日)
清水寺北斗堂の辺りに落雷がある(歴代皇紀)。
◆寛元元年5月29日(1243年6月17日)
円満院に落雷がある(百練抄)。
◆寛元3年1月1日(1245年1月30日)
鎌倉の鶴岡八幡宮に落雷がある(平戸記、吾妻鏡、史料綜覧)。
◆寛元3年7月1日(1245年7月1日)
少将四条隆兼の屋敷に落雷があり、建物が破損する(平戸記)。
◆建長6年6月17日(1254年8月1日)
東大寺の勅封倉が落雷のため炎上する(帝王編年記、分類本朝年代記)。
◆建長7年8月28日(1255年9月30日)
法勝寺の九重塔に落雷があり、火災が発生する(歴代皇紀、一代要記、百練抄)。
◆康元元年6月16日(1256年7月9日)
法勝寺の阿弥陀堂に落雷がある(史料綜覧)。
◆弘長3年9月12日(1263年10月15日)
鎌倉の武蔵大路に落雷がある(吾妻鏡)。
◆文永元年6月27日(1264年7月22日)
吉野大塔・蔵王堂などが落雷のため全焼(新抄、皇年代略記、興福寺年代記)。
◆文永5年6月5日(1268年7月16日)
法勝寺九重塔に落雷がある(吉続紀)。
◆文永7年4月21日(1270年5月12日)
東寺の塔に落雷があり、焼失する(高野春秋輯録)。
◆建治3年7月26日(1277年5年12日)
興福寺の金堂・講堂などが落雷による火災で被害をうける(興福寺略年代記、法隆寺別当次第、大日本史、皇年代略記、和漢合運指掌図、分類本朝年代記)。
◆弘安7年6月27日(1284年8年9日)
六条殿中門に落雷がある(続史愚抄、勘仲記)。
◆弘安9年4月20日(1286年5年20日)
法勝寺の塔に落雷がある(勘仲記)。
◆永仁3年7月30日(1295年9年10日)
大安寺の塔に落雷があり、炎上する(興福寺略年代記)。
◆正中2年6月15日(1325年7年25日)
塩小路西洞院に落雷がある(史料綜覧)。
◆正中2年6月25日(1325年8年4日)
比叡山無動寺に落雷があったため山崩が発生し、30以上の坊舎に被害がでる(神明鏡、桜雲記、史料綜覧、続史愚抄)。
◆延元2年7月28日(1336年9年4日)
鎌倉の鶴岡神社の鳥居に落雷があり、破損する(鶴岡社務記録)。
◆延元2年6月13日(1337年7月11日)
東寺の塔に落雷があり、焼失する(東寺長者補任、高野春秋輯録)。
◆正平11年2月17日(1356年3月19日)
興福寺の塔および金堂が落雷により焼失する(興福寺略年代記、続史愚抄)。
◆正平12年閏7月9日(1357年8月24日)
信貴山毘沙門堂で落雷のため1人が亡くなり、建物の柱が破損する(法隆寺別当次第)。
◆正平17年1月13日(1362年2月8日)
東大寺の七重塔が落雷により焼失する(喜元記、大乗院日記目録)。
◆正平21年7月15日(1366年8月21日)
平野神社に落雷がある(続史愚抄、史料綜覧)。
◆建徳元年8月15日(1370年9月5日)
前関白九条経教の屋敷に落雷があり、2人が落雷がある(後愚昧記)。
◆元中2年5月11日(1385年6月19日)
賀茂太田神社に落雷がある(続史愚抄)。
◆元中6年1月22日(1389年2月18日)
東寺の塔に落雷があり、柱が破損する(東寺王代記)。
◆応永10年6月3日(1403年6月22日)
相国寺の塔に落雷があり、焼失する(兼宣公記、続史愚抄、史料総覧、和漢合運指掌図、分類本朝年代記)。
◆応永13年9月12日(1406年10月23日)
清水寺の塔に落雷があり、焼失する(兼宣公記、続史愚抄、史料総覧、武家年代記、南方紀伝、教言卿記)。
◆応永18年閏10月15日(1411年11月30日)
興福寺の塔、金堂が落雷のため焼失する(東寺執行日記、興福寺別当次第)。
◆応永23年1月9日(1416年2月7日)
落雷のため北山大塔が焼失する(歴代皇紀、如是院年代記、満済准后日記)。
◆応永31年7月15日(1424年8月21日)
赤松左京大夫の家に落雷がある(満済准后日記、兼宣公記)。
◆応永32年閏6月13日(1425年7月27日)
南禅寺の塔が落雷により焼失する(続史愚抄)。
◆応永33年5月9日(1426年6月14日)
賀茂神社周辺に落雷がある(薩戒記)。
◆永享6年6月16日(1434年7月22日)
稲荷山の大杉に落雷がある(満済准后日記)。
◆永享8年6月14日(1436年7月27日)
東寺の塔に落雷がある(東寺王代記、続史愚抄、東寺執行日記、東寺長者補任)。
◆永享11年6月(1439年7月11日から8月9日)
東寺の塔に落雷がある(史料綜覧)。
◆文安2年6月22日(1445年7月26日)
左大臣近衛房嗣の屋敷の門に落雷がある(続史愚抄)。
◆文安3年7月24日(1446年8月16日)
一条西洞院百萬遍堂に落雷がある(史料綜覧)。
◆宝徳3年7月19日(1451年8月15日)
東大寺南大門に落雷がある(続史愚抄、野史)。
◆文正元年7月10日(1466年8月20日)
一条成菩薩寺、祇園塔報慈院等に落雷がある(陰涼軒日録、史料総覧)。
◆応仁元年5月16日(1467年6月17日)
元興寺に落雷があり、天王像が破損する(大乗院寺社雑事記)。
◆文明2年10月3日(1470年10月26日)
相国寺の七重塔が落雷により火災が発生する(親長卿記、史料綜覧、応仁記、野史、和漢合符)。
◆文明8年2月25日(1476年3月20日)
平野神社に落雷がある(続史愚抄、實隆公記、分類本朝年代記)。
◆文明11年1月1日(1479年1月23日)
吉野上社、播磨国(兵庫県の南西部)書寫山に落雷があり、書寫山の塔が焼失する(大乗院寺社雑事記、實隆公記)。
◆延徳元年6月10日(1489年7月8日)
関白一条冬良の屋敷に落雷がある(親長卿記、實隆公記、続史愚抄、大乗院寺社雑事記)
◆延徳元年8月11日(1489年9月6日)
伊勢外宮が落雷のため、炎上する(分類本朝年代記)。
◆延徳2年9月14日(1490年10月27日)
伊勢外宮が落雷のため、炎上する(分類本朝年代記)。
◆明応3年6月1日(1494年7月3日)
京の一条烏丸に落雷がある(史料綜覧)。
◆文亀元年5月3日(1501年5月19日)
奈良の四恩院に落雷がある(史料綜覧)。
◆永正2年1月30日(1505年3月5日)
法京堂、本法寺に落雷がある(二水記、史料綜覧)。
◆大永7年6月8日(1527年7月6日)
京で落雷のため、男女2名が亡くなる(二水記、言継卿記)。
◆天文元年5月27日(1532年6月30日)
清水寺に落雷があり、巡礼堂等が破損する(言継卿記、続史愚抄、厳助往年記)。
◆永祿6年4月2日(1563年4月24日)
東寺の塔に落雷あり、炎上する
(御湯殿上日記、長享年後畿内兵乱記、言継卿記)。
◆天正3年6月29日(1575年8月5日)
高山に落雷がある(史料綱文)。
◆天正16年5月(1588年5月26日から6月23日)
聚楽第(豊臣秀吉が造成した桃山文化を代表する荘厳・華麗を極めた城郭風の邸宅)へ落雷があり、2名が負傷する(当代記)。
◆文祿2年8月11日(1593年9月6日)
京の長妙寺の周辺に落雷がある(立入左京亮入道隆佐記)。
◆文祿3年7月22日(1594年9月6日)
東寺の塔に落雷があり、炎上する(分類本朝年代記)。
◆文祿4年5月(1595年6月8日から7月6日)
中納言徳川秀忠(徳川幕府2代将軍)の屋敷に落雷がある(当代記)。
◆慶長7年10月3日(1602年6月8日)
加賀国(石川県の南西部)金沢城に落雷があり、天守閣等を焼失する(加賀藩史料、当代記、史料綱文、分類本朝年代記)。
参考文献
- 「日本の災害史(第1巻〜第4巻)」(著者 三浦幸一郎 発行所 三浦幸一郎)
- 「日本史小百科 災害」(著者 荒川秀俊、宇佐美龍夫 発行所 近藤出版社)
- 「日本の天災・地変 上・下」(編集 東京府社会課 発行所 原書房)
- 「日本史分類年表」(著者 桑田忠親 発行所 東京書籍)
- 「雷の話」(著者 神田選吉 発行所 電友社)
- 「名前から引く人名辞典」(編集 日外アソシエーツ 発行所 日外アソシエーツ)
- 「日本史総覧」(監修 児玉幸多/他 発行所 新人物往来社)
- 「国史大系」(編集 黒板勝美、国史大系編修会 発行所 古川弘文館)
- 「日本叢書索引」(編修 広瀬敏 発行所 名著刊行会)
- 「古典籍総合目録」(編集 国文学研究資料館 発行所 岩波書店)
前のページへ|
次のページへ
落雷による事故が記載されている元の文献へ
雷の事故のページへ