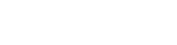近世における落雷による事故1
◆慶長13年6月22日(1608年8月2日)
豊後国(現在の大分県の中南部)杵築城に落雷があり、焼失する(松井家請)。
◆慶長14年3月1日(1609年4月5日)
武蔵国で落雷により農家十七八戸が被害をうける(当代記、徳川実紀)。
◆慶長14年5月29日(1609年6月30日)
美濃国(現在の岐阜県の中南部)で落雷により、1名が亡くなる(当代記)。
◆元和7年6月20日(1621年8月7日)
山城国上賀茂で落雷により、死者がでる。(野史、史料綱文)。
◆寛永4年9月5日(1627年10月13日)
越中国(現在の富山県のあたり)高岡城のシャチホコに落雷があり、出火する(津軽信政公事蹟)。
◆寛永7年9月18日(1630年10月23日)
大光寺の三重の塔に落雷があり、焼失する(工藤家記)。
◆寛永7年10月7日(1630年11月11日)
高野山の塔に落雷があり、炎上する(高野春秋輯録)。
◆寛永10年6月19日(1633年7月24日)
江戸の鷹坊に落雷がある(徳川実紀)。
◆寛永12年6月16日(1635年7月29日)
諏訪神社に落雷がある(香取郡誌)。
◆寛永19年5月21日(1642年6月18日)
江戸市中に落雷があり、3名が負傷する(東京市史稿)。
◆正保2年5月27日(1645年7月20日)
江戸市中に落雷があり、伊達遠江守の家来が死亡する(徳川実紀、東京市史稿)。
◆正保4年7月19日(1647年8月19日)
松平長門守の下屋敷の周辺に落雷がある(東京市史稿)。
◆慶安3年5月10日(1650年6月8日)
伊達遠江守の屋敷に落雷があり、家来2名が死亡する(東京市史稿)。
◆承応3年6月17日(1654年7月30日)
水戸家の屋敷に落雷があり、3名が死亡する(徳川実紀)。
◆明暦元年8月10日(1655年9月9日)
三河国で火薬庫に落雷があり、周囲の建物に被害がでる(徳川実紀)。
◆万治3年6月18日(1660年7月25日)
大阪城に落ちた雷により火薬庫が爆発、町屋1481軒が破損、死傷者120人以上その他多大な被害がでる(皇年代私記、徳川実紀、和漢合運指掌図、分類本朝年代記、玉露叢)。
◆万治3年8月4日(1660年9月8日)
松平右衛門佐光之の屋敷に落雷がある(徳川実紀)。
◆寛文2年8月3日(1662年9月15日)
讃岐国(現在の香川県のあたり)高松城に落雷があり、多くの武器が灰燼にきす(香川県史)。
◆寛文5年1月2日(1665年2月16日)
落雷により大阪城の天守閣・糒倉が炎上する(皇年代私記、徳川実紀、玉露叢、分類本朝年代記、和漢年契、続日本王代一覧)。
◆寛文5年6月2日(1665年7月14日)
江戸市中20ヶ所以上に落雷があり、井上河内守上屋敷で家来1名が死亡したほか、御三家のうちの一つ尾張家、越後中将屋敷、戸田相模守屋敷、松平大隈守屋敷、丹羽左京大夫屋敷等に被害がでる(徳川実紀、東京市史稿、山鹿素行先生日記)。
◆寛文7年10月18日(1667年12月3日)
越後国(佐渡島を除く現在の新潟県のあたり)村上城に落雷があり、天守閣等が焼失する(続皇年代記、徳川実紀)。
◆寛文12年2月19日(1672年3月18日)
肥後国(現在の熊本県のあたり)八代城の城郭に落雷があり、48人死亡、天守閣・櫓などが炎上する(九州の災害史、日本史分類年表)。
◆延宝2年6月11日(1674年7月14日)
京の廬山寺堂に落雷がある(続史愚抄、玉露叢、久夢日記)。
◆延宝2年6月12日(1674年7月15日)
諏訪神社に落雷がある(香取郡誌)。
◆延宝5年7月5日(1677年8月3日)
御春屋、前右大臣一条教輔の屋敷に落雷があり、被害がでる(続史愚抄)。
◆延宝6年5月23日(1678年7月11日)
戸田越前守の長屋に落雷がある(山鹿素行先生日記)。
◆延宝8年3月(1680年3月11日から4月27日)
沖縄島に落雷があり、死者がでる(球陽)。
◆天和元年2月23日(1681年4月11日)
美濃国園通寺に落雷があり、本堂・客殿等が焼失する(大垣市史)。
◆天和元年12月13日(1682年1月21日)
伊勢内宮夜宝殿に落雷があり、炎上する(分類本朝年代記)。
◆天和2年5月4日(1682年6月9日)
江戸浅草に落雷があり、死者がでる(山鹿素行先生日記)。
◆天和2年7月1日(1682年8月3日)
江戸数十ヶ所に落雷があり、人的物的被害が出る(山鹿素行先生日記、徳川実紀)。
◆貞享3年閏3月25日(1686年4月17日)
因幡国(鳥取県東部)鳥取城に落雷があり、天守閣に被害がでるまた、石見国(鳥取県西部)津和野城にも落雷があり、多大な被害がでる(因府年表、徳川実紀、続日本王代一覧)。
◆貞享4年4月5日(1687年5月15日)
日光で落雷があり、大谷川にかかる橋に落雷がある(徳川実紀)。
◆元禄3年8月15日(1690年9月17日)
前内大臣今出川公規の屋敷、妙顕寺の塔などに落雷がある(続史愚抄)。
◆元禄4年7月6日(1691年7月30日)
日光山本地堂の近くに落雷がある(徳川実紀、元和日記)。
◆元禄5年10月2日(1692年11月9日)
越後国国分寺に落雷があり、本尊が焼失する(日本史小百科)。
◆元禄5年11月11日(1692年12月18日)
鳥取城の天守閣に落雷がある(因府年表、続皇年代記)。
◆元禄6年5月10日(1693年6月13日)
春日大社に落雷がある(続史愚抄)。
◆元禄6年9月5日(1693年10月4日)
頂妙寺に落雷がある(続史愚抄)。
◆元禄13年2月25日(1700年4月14日)
大坂城に落雷がある(徳川実紀、元和日記)。
◆元禄13年7月4日(1700年8月18日)
豊前国(現在の福岡県東部と大分県北部に相当する)小倉城の天守閣に落雷がある(福岡県災異史誌)。
◆元禄13年7月6日(1700年8月20日)
霊元上皇の対屋に落雷がある(続史愚抄)。
参考文献
- 「日本の災害史(第1巻〜第4巻)」(著者 三浦幸一郎 発行所 三浦幸一郎)
- 「日本史小百科 災害」(著者 荒川秀俊、宇佐美龍夫 発行所 近藤出版社)
- 「日本の天災・地変 上・下」(編集 東京府社会課 発行所 原書房)
- 「日本史分類年表」(著者 桑田忠親 発行所 東京書籍)
- 「雷の話」(著者 神田選吉 発行所 電友社)
- 「名前から引く人名辞典」(編集 日外アソシエーツ 発行所 日外アソシエーツ)
- 「日本史総覧」(監修 児玉幸多/他 発行所 新人物往来社)
- 「国史大系」(編集 黒板勝美、国史大系編修会 発行所 古川弘文館)
- 「日本叢書索引」(編修 広瀬敏 発行所 名著刊行会)
- 「古典籍総合目録」(編集 国文学研究資料館 発行所 岩波書店)
前のページへ|
次のページへ
落雷による事故が記載されている元の文献へ
雷の事故のページへ